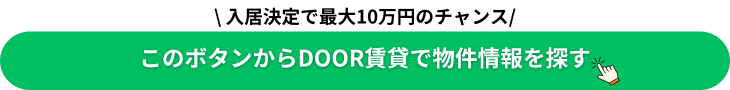投稿日:2025年4月30日 | 最終更新日:2025年4月30日

1LDKは、一人暮らし向けの間取りとしては広い間取りです。そのため、「持て余さない?」「レイアウトが難しいかも」など、物件探しの際は悩むかもしれません。
そこで今回は、一人暮らし×1LDKについて、間取りの特徴やレイアウトのコツを解説します。1LDKの家賃相場も解説するので、「自分に合う間取りなのか」を判断してみてください。
一人暮らし向け1LDKとは?特徴や家賃相場

一人暮らし向けの1LDKについて、間取りの特徴や家賃相場を解説します。
1LDKは「リビング/ダイニング/キッチン+居室」
1LDKは以下の特徴がある間取りです。
1LDKの特徴
・LDK(リビング/ダイニング/キッチン)+居室で構成される
・LDKは8畳以上
・各スペースは独立している
【1LDKの間取り例】
1LDKは、リビング・ダイニング・キッチンを一体化させた空間と、和室or洋間の居室で構成されます。
空間が広く、大型家具・インテリアや家電も設置しやすいため、自分好みの生活環境を整えやすい間取りです。
1LDKは一人暮らしに十分な広さ
1LDKの広さは約30~50㎡が相場で、一人暮らしには十分な間取りです。
国土交通省によると、「健康で文化的な住生活の基礎」として求められる広さは25㎡とされています。1LDKは十分な広さがあるため、快適に過ごしやすい間取りと言えるでしょう。
※出典:国土交通省 住生活基本計画における「水準」について
【地域別】1LDKの家賃相場
1LDKの家賃相場を地域別に紹介します。
上記はあくまでも目安なので、立地や設備、築年数によって家賃は変動します。
1LDKは2人世帯にも需要のある間取りなため、都心部の場合は10~20万円/月を超えるケースもあります。
一人暮らし向けの1DK・1LDKの違い

一人暮らし向けの1DK・1LDKの違いを見ていきましょう。
1DK・1LDKの違い
| 間取り | 部屋数 | 部屋の種類 | 広さの目安 | 部屋の広さ | 家賃相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DK | 2部屋 | ・ダイニングキッチン ・居室 | 約30㎡ | 4.5~8畳未満 ※DKの広さ | 4.88万円 |
| 1LDK | 2部屋 | ・リビング/ダイニング/キッチン ・居室 | 約30~50㎡ | 8畳以上 ※LDKの広さ | 6.61万円 |
※家賃相場は全国平均(2025年4月時点)
1DKはダイニング・キッチンを1つの部屋として独立させた間取りです。1LDKとは異なり、リビングとしての用途が想定されていません。
あくまでも定義上の違いなので、イメージとしては「ダイニングキッチンの広さ」が異なると理解しておきましょう。
一人暮らしで1LDKに住むメリット

一人暮らしで1LDKに住むメリットを見ていきましょう。
1LDKのメリット
・面積が広いため、大型家具・家電や好きなインテリアを配置しやすい
・生活空間をわけられるため、日常にメリハリが出る
・友人や恋人を招きやすい
・ライフステージの変化に強い(同棲や結婚など)
1LDKの強みは専有面積の広さです。ソファやダイニングテーブル、大型冷蔵庫などを配置してもスペースに余裕があるでしょう。
また、「単身者専用」という制限がない賃貸物件も多いため、将来的に同棲や結婚も視野に入れて入居できます。ライフステージの変化に合わせやすく、引越しの手間・コストも省けます。
一人暮らしで1LDKに住むデメリット

一人暮らしで1LDKに住むデメリットは次のとおりです。
1LDKのデメリット
・1DKより家賃相場が約2万円高い
・光熱費が高くなりやすい
・家事の手間や負担が増える
1LDKは1DKより専有面積が広いため、家賃も高額です。家賃の目安は収入の1/3~1/4が目安とされているため、家賃相場(6.61万円)を参考にすると約26万円以上の収入が必要でしょう。
さらに、照明やエアコンの設置台数も増えるため、光熱費も高くなりがちです。
また、専有面積が広い部屋は、掃除の範囲や洗濯物を運ぶ距離が広くなり、家事の手間・負担も増えます。「生活費のやりくり」「効率的な家事」が苦手な人にとって、1LDKはデメリットのある間取りかもしれません。
一人暮らし×1LDKが向いている人

一人暮らしに1LDKが向いている人の特徴をご紹介します。自分のライフスタイルと照らし合わせてチェックしてみてください。
用途別に空間を使い分けたい人
仕事・作業や寝室、趣味など用途別に空間を使い分けたい人は、1LDKがおすすめです。1LDKは、LDKが8畳以上、居室は4畳以上の広さが目安の間取りです。
LDKをパーティションや本棚などで区切ると、「食事用+仕事用」「趣味用+作業用」など用途に応じて空間を使い分けられます。
休日・仕事・趣味・就寝を明確に切り分け、生活にメリハリを持たせたい人は1LDKを検討しましょう。
ライフステージの変化(同棲・結婚)を想定している人
同棲や結婚などライフステージの変化を想定している人は、1LDKを検討してみてください。
賃貸物件の中には単身者限定の物件があり、2人以上の入居を許可されないケースもあります。このような場合、同棲やルームシェアを始める際は引越しせざるを得ません。
しかし、1LDKは複数名の入居を想定した賃貸物件も多いため、ライフステージの変化に合わせやすい間取りです。将来的な同棲・結婚を想定している人は1LDKも選択肢に加えましょう。
自分らしいライフスタイルを確立したい人
部屋の雰囲気や家具・インテリアへのこだわりなど、自分らしいライフスタイルを確立したい人にも1LDKはおすすめです。
快適な空間づくりには、「家具・家電の占める面積を1/3とする」ことが目安とされています。1LDKの場合、LDKと居室で12畳以上は確保されるので、少なくとも4畳分は家具・家電を設置しても窮屈な印象を与えません。
ベッドやソファ、冷蔵庫、テレビ台など大型家具を設置しても、空間には余裕があります。「自分らしさのある部屋づくり」を実現しやすいため、ライフスタイルへのこだわりがある人には1LDKがおすすめです。
一人暮らし向け1LDKの間取りの種類

一人暮らし向け1LDKの間取りの種類を4パターンご紹介します。
コンパクトな単身者向けタイプ
単身者向けの1LDKは専有面積が30~35㎡ほどで、一人暮らしでも持て余しにくい間取りです。
単身者向けの特徴
・LDKと居室(寝室)がつながっている
・光熱費を抑えやすい
・部屋のレイアウトを考えやすい
コンパクトな1LDKであれば、エアコンや照明の数が少なく、余計な光熱費を発生させません。さらに、家具やインテリアの数・サイズも制限されるため、レイアウトが苦手な人でも配置に困る心配は少ないでしょう。
各部屋が独立するタイプ
各部屋が独立するタイプは、プライベートな空間を確保しやすい間取りです。
独立タイプの特徴
・居室とLDKが個別にわかれ、廊下から居室へ入室できる
・居室が独立しているため、プライベートな空間を確保できる
独立タイプは、LDKとしてオーソドックスな間取りです。同棲やルームシェアを始めても、生活音は気になりにくいでしょう。
縦長タイプ
縦長タイプは、玄関から順にLDK・居室へと続く間取りです。
縦長タイプの特徴
・壁の面積が多く、家具を配置しやすい
・キッチン側から見る奥行が広く、解放感がある
・家事動線が直線的で利便性が高い
縦長タイプはLDKと居室が直線的につながっているため、奥行きのある間取りです。ベッドやテーブル、ソファなど縦・横長の家具を配置しやすく、レイアウトが簡単な間取りとも言えます。
横長タイプ
横長タイプは、玄関側から見て居室とLDKが横に並んだ間取りです。
横長タイプの特徴
・居室とLDKに窓(ベランダ)があり、光を取り込みやすい
・家事動線が短く、掃除や洗濯の負担を抑えられる
・大型家具を配置しても窮屈な印象になりづらい
横長タイプは、脱衣所・キッチンから各部屋までの距離が短い間取りです。掃除・洗濯や食器の片付けなど、家事の手間を抑えられます。
また、居室とLDKが横につながっているため、広々とした印象です。本棚や収納棚など大型家具を配置しても、圧迫感を抑えつつレイアウトできるでしょう。
一人暮らし×1LDKをレイアウトする6つのコツ

一人暮らしの1LDKで上手にレイアウトするコツを6つ解説します。
各スペースの使い方を考える
居室・LDKの使い方を考えておくと、必要な家具・家電や適切なサイズ感を把握しやすくなります。
1LDKのように空間の広い間取りは、スペースごとの使い方を決めていないと、空間を上手に活用できません。たとえば、「コタツはマストでほしい!」「○○のソファを置きたい」など、家具を優先的に決めてしまうと、家事動線や部屋の印象が雑多になりがちです。
そのため、「リビングでは映画を観てくつろぐ」「LDKに作業スペースを作る」など、使い方から考えましょう。使い方が明確になれば、必要な家具の種類やサイズ、適切な配置方法なども決められます。
暮らしやすい環境を整えたい場合は、まず各スペースの使い方から考えましょう。
収納はスペース別に設ける
部屋の収納は各スペースごとに配置すると、生活上の利便性を高められます。
1LDKのように広い間取りは、日用品や衣類を一箇所にまとめてしまうと、必要なものが取り出しづらくなります。さらに、ものが多くなれば収納を圧迫し、部屋の中に溢れるかもしれません。
そのため、寝室やリビング、作業場所などスペースごとに収納を作り、分散させましょう。必要なものを取り出しやすく、部屋の中もスッキリした見た目に保ちやすくなります。
床の60~70%に余白をつくる
床の60~70%が見えるよう家具・インテリアを配置すると、圧迫感のない「垢抜けた印象の部屋」に仕上がります。
家具・インテリアの充実した部屋は機能的で、上手に配置するとこだわりを感じさせるレイアウトに仕上げられます。しかし、レイアウトのノウハウがなければ雑多な印象になり、理想的な空間は作れません。
部屋のレイアウトに慣れない人は、床の2/3が余白として残るよう家具・インテリアを配置してみましょう。窮屈な印象を避けやすく、自然とバランスの良い配置が作れます。
部屋のカラーは3色に抑えて統一感を出す
部屋のカラーを3色に抑えると、全体的な統一感を出しつつ、くつろぎやすい空間が作れます。
部屋の家具・インテリアは常に目に付き、まとまりがないと違和感を覚えます。カラーによっては気持ちが落ち着かず、くつろげないかもしれません。
そのため、家具・インテリアはカラーリングに配慮して、部屋全体をレイアウトしましょう。
カラーリングについて
・ベースカラー(7割) :壁や天井、床などの色
・メインカラー(2割) :ラグやカーテンなど存在感のある家具・インテリアの色
・アクセントカラー(1割):観葉植物や小物などの色
全体をベースカラーに寄せることで、まとまりのある印象に仕上げられます。中でも、ラグやカーテン、ソファなどの大型家具・インテリアは目立ちやすいため、カラーを統一しましょう。
アクセントカラーはベース・メインカラーとは異なる色を使うことで、全体の印象に変化を加えられます。
背の低い家具で空間を広く見せる
背の低い家具は視線を遮らず、部屋を広く見せる効果に期待できます。
どれだけ空間の広い部屋でも、大きな家具を配置しすぎると圧迫感が出てきます。背の高い本棚やソファは視線を遮り、部屋の奥行きが感じにくくなるでしょう。
リラックスできる空間を作るには、背の低い家具を中心に配置することがポイントです。本棚や収納棚は、背板のないものを選ぶと抜け感があり、より空間が広く感じられます。
家事動線を意識する
家事動線を意識したレイアウトは、生活の利便性を向上させられます。
家事動線を意識するコツ
・各スペース(ベランダやキッチンなど)同士をつなぐ通路を考える
・幅90㎝を目安に家事動線を作る
・家具やインテリアの扉の開閉も考慮する
家事動線を考える際は、具体的な生活の流れをイメージしましょう。たとえば、テレビ前のソファ→脱衣所→ベランダの流れを意識した場合、洗濯物を干すまでの動線を確保できます。
また、家具・インテリアに扉が付いている場合、開いた状態で動線を塞がないか確認しましょう。実際の間取り図を使い、家具を図面上で配置すると、家事動線が把握しやすくなります。
使い方・レイアウトに気を付けると一人暮らしでも1LDKは持て余さない
1LDKはLDK+居室で構成された間取りで、専有面積の目安は30~50㎡ほどあります。一人暮らしとしては十分な広さがあり、好みの家具・インテリアも設置しやすいでしょう。
ただし、家具・インテリアへのこだわりを優先するのはNGです。家事動線や部屋の印象を配慮できなくなり、暮らしにくい環境を作る恐れがあります。
大切なのは、部屋の使い方やレイアウトのコツを理解することです。>>一人暮らし×1LDKをレイアウトする6つのコツを参考に、自分らしい暮らしを実現しつつ、利便性の高い部屋づくりを実践してみましょう。
また、理想の賃貸物件を探す際は「DOOR賃貸」がおすすめです。人気不動産ポータルサイトの情報がまとめて掲載され、1サイトで賃貸物件が探せます。
●人気サイトの物件をまとめて掲載!DOOR賃貸でお部屋探しが完結!
●ペット可や防音/楽器可など見つかりにくい賃貸物件も見つかりやすい!
●入居決定で10万円がもらえるチャンス!