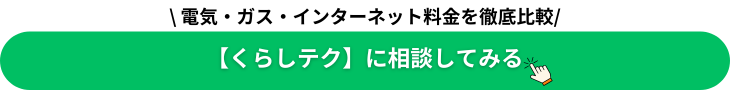投稿日:2025年3月28日 | 最終更新日:2025年5月16日

光熱費の中でも、特に大きな割合を占める電気代。昨今は電気代の値上がりにより、生活費の圧迫を心配するケースも多いかもしれません。
そこで今回は、一人暮らしの電気代事情について、平均額や値上がりの理由、節約方法を解説します。電気代の内訳・計算方法も解説するので、本格的な節約に取り組みたい人はぜひ参考にしてみてください。
一人暮らしの場合、電気を使うのは主に自分だけです。原因と対策がわかれば、毎月の電気代をコンスタントに節約できます。
一人暮らしの電気代 | 1ヶ月の平均額(相場)

一人暮らしにかかる電気代の平均額について、1ヶ月・季節別・地域別に見ていきましょう。
自宅の電気代と比較して高い場合は、後述する>>一人暮らしの電気代が高くなる6つの理由もチェックしてみてください。
一人暮らしの電気代平均は6,756円/月
総務省の調査によると、一人暮らしにおける1ヶ月あたりの電気代は6,756円が平均額です。
※出典:総務省 統計局 家計調査 1世帯当たり1か月間の収入と支出(2024年)
ただし、季節や地域によって、稼働する家電の種類・稼働時間は異なります。次項の季節別・地域別の電気代平均も参考に、自宅の電気代がどのくらい高いのか見ていきましょう。
【季節別】一人暮らしの電気代平均
季節別の電気代平均は次のとおりです。
季節別の電気代平均
| 季節 | 電気代平均 |
|---|---|
| 冬(1~3月) | 7,150円 |
| 春(4~6月) | 5,839円 |
| 夏(7~9月) | 6,771円 |
| 秋(10~12月) | 6,356円 |
夏・冬など部屋の中と外で寒暖差のある時期は、空調設備の消費電力が多くなり、電気代が高くなりがちです。
電気代を節約する際は、夏・冬にかけてエアコンの使い方を工夫しましょう。詳しくは>>家電製品(エアコン・冷蔵庫・照明)の正しい使い方を覚えるで解説します。
【地域別】一人暮らしの電気代平均
地域別の電気代平均は次のとおりです。
地域別の電気代平均
| 地域 | 電気代平均 |
|---|---|
| 北海道・東北地方 | 7,500円 |
| 関東地方 | 6,566円 |
| 北陸・東海地方 | 6,794円 |
| 近畿地方 | 6,648円 |
| 中国・四国地方 | 7,437円 |
| 九州・沖縄地方 | 6,274円 |
地域によって電気代に差が出る理由は次のとおりです。
電気代に差が出る理由
・寒い地域ほど空調設備による消費電力が大きくなる
・原子力発電の稼働状況の違い
室内外の寒暖差が激しいほど、空調設備は高い出力で稼働しなければならないため、消費電力が大きくなります。北海道や東北の場合、気温が氷点下に達する時期もあり、電気代が高くなりがちです。
また、近畿・九州地方は原子力発電の比率が他の地域よりも高く、発電にかかる燃料費も抑えられています。
一人暮らしにかかる電気代の内訳(計算方法)
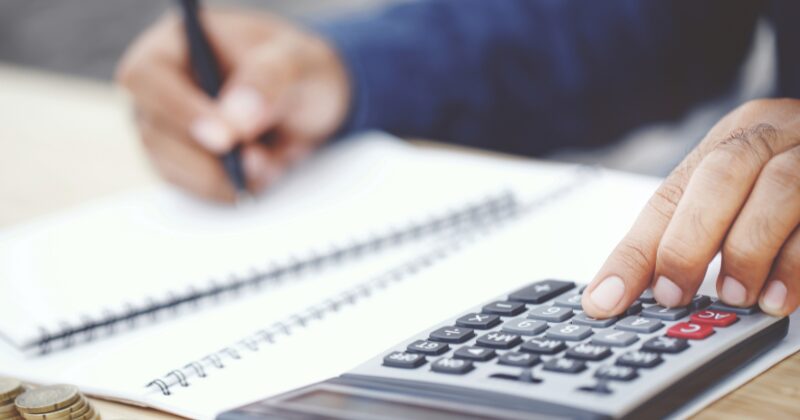
電気代を節約するには、電気代の内訳(計算方法)を知り、自分の暮らしに合った料金プランを契約することが大切です。
内訳の詳細
・基本料金 :定額で支払う料金であり、契約アンペアに応じて変動する
・電力量料金 :電力使用量と料金単価を乗じて算出される
・燃料費調整額:発電に必要な燃料の市場価格が反映される
・再生可能エネルギー発電促進賦課金:再生可能エネルギーの買取にかかる費用
自分で調整できるのは、電力量料金と基本料金(契約アンペア)です。電力量料金の節約方法ついては、>>一人暮らしの電気代を節約する5つの方法で詳しく解説します。
また、一人暮らしに適切な契約アンペアは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

家電製品の電気代を計算する方法
家電製品の電気代を計算する方法も解説します。
たとえば、消費電力が100W、使用時間を2時間、電力量料金単価を30円とした場合、以下のように算出されます。
電気代 : 0.1kWh×2時間×30円=6円
各家電製品の電気代を計算することで、どの家電の使用頻度を下げるべきか判断しやすくなります。
一人暮らしの電気代が高くなる6つの理由

一人暮らしで電気代が高くなる理由を6つ解説します。普段の生活と照らし合わせて、隠れた原因がないかチェックしましょう。
電力会社・電気料金プランが暮らしにマッチしていない
電気料金プランは単価や基本料金で毎月の電気代に差が出るため、自分の生活にマッチしたタイプを選ぶ必要があります。
電力会社によっては、夜間帯のみ従量料金単価が安いプランも提供されています。日中は仕事で自宅にいない場合、電気代を安く抑えられるでしょう。
また、家電製品の使い方に合わないアンペア数を契約している場合、余計な基本料金を支払っている恐れもあります。約中の料金プランを確認し、自分のライフスタイルや電気の使い方にマッチしているかチェックしてみてください。
適切な契約アンペアについては、以下の記事で詳しく解説しています。

家電製品(エアコン・冷蔵庫・照明)の使い方を間違えている
以下の家電製品は消費電力が大きく、正しい使い方をしなければ電気代を抑えられません。
消費電力の大きな家電製品とNGな使い方
| 家電製品 | NGな使い方 |
|---|---|
| エアコン | ・ON / OFFを短時間に何度も切り替える ・フィルター掃除をしていない ・極端な温度設定にしている ・室外機の周囲にモノを置く |
| 冷蔵庫 ※冷凍庫を除く | ・食品を隙間なく詰め込む ・温かいままの食品を入れる ・設定温度を強に設定している |
| 照明 | ・不在時でも付けっぱなし ・LED未使用 |
中でもエアコンは、稼働直後(設定温度に達するまで)が最も電力を消費します。何度も付けたり、消したりしていると、電気代が高くなるため注意してください。
冷蔵庫・照明は稼働時間が長いため、>>家電製品(エアコン・冷蔵庫・照明)の正しい使い方を覚えるも参考に、節電方法を頭に入れておきましょう。
家電の省エネ性能が低い
古い家電は省エネ性能が低く、消費電力も大きくなりがちです。
経済産業省 資源エネルギー庁によると、2013年~2023年における家電製品の消費電力は、以下のように推移しました。
10年以上前の家電製品は消費電力が大きく、最新家電ほどの節電効果は見込めません。電気代の節約をコンスタントに続けるには、家電の買い替えも検討しましょう。
家電の買い替えについては、>>省エネ家電への買い替えで詳しく解説します。
在宅時間が増えた
テレワークなどで在宅時間が増えた場合、エアコンやPCなどの稼働時間が増えるため電気代も高まります。
具体的にどのくらい差があるのか、テレワークの有無で電気代をシミュレーションしてみましょう。
テレワーク有無での電気代比較
| 日数 | テレワークなし ※4時間稼働 | テレワークあり ※12時間稼働 |
|---|---|---|
| 1日 | 99.6円 | 298.8円 |
| 1週間 | 697.2円 | 2,091.6円 |
| 1ヶ月(30日) | 2,988円 | 8,964円 |
※業務+プライベートでの家電の稼働を想定
上記はあくまでも概算なので、家電製品の消費電力や料金プランによって金額は変動します。
しかし、稼働時間が長くなるほど電気代は高くなるため、在宅時間の調整も検討しましょう。
世界情勢の変化
世界情勢の変化により燃料価格が高騰し、個人宅の電気代も影響を受けました。
世界情勢の変化とは
・新型コロナウイルス蔓延による経済の停滞
・世界的な脱炭素推進による天然ガスの需要増加
・ウクライナ情勢の影響による、ロシアからの化学燃料の輸出制限
・2022年からの円安による輸入価格高騰
日本では火力発電による電力供給が60%を超えており、石炭や化石燃料などが不可欠です。
しかし、世界情勢の変化によって燃料価格が高騰し、電気代へも反映されています。個人でできる対策には限りがあるものの、>>一人暮らしの電気代を節約する5つの方法も参考に、日々の節電を意識しましょう。
2025年4月分以降は「電気・ガス料金支援」から外れる
2025年4月分以降は「電気・ガス料金支援」の対象期間から外れるため、電気代が高くなります。
電気・ガス料金支援とは、高騰する電気代を抑えるため、月々の電気使用量に応じた料金を値引きする政府の施策です。
電気・ガス料金支援の詳細
| 項目 | 内容 | ||
| 対象期間 | 2025年1月使用分~3月使用分 | ||
| 値引き単価 | 2025年1・2月使用分 | 2.5円/kWh | |
| 2025年3月使用分 | 1.3円/kWh | ||
空調設備(暖房)の使用頻度が高い時期を対象に、電気使用量に応じた値引きが実施されます。
一人暮らしの電気使用量(1~3月)の平均は300kWh/月です。この場合、約750円/月の値引きが受けられます。
しかし、2025年4月以降は支援継続が未定なため、電気代は値上がりするかもしれません。
一人暮らしの電気代を節約する5つの方法

一人暮らしの電気代をコンスタントに節約する方法を5つご紹介します。
電力会社・料金プランを乗り換える
電力会社や料金プランを乗り換えることで、数百円~数千円/月の電気代を節約できるかもしれません。
日本では、2016年4月からの電力自由化に伴い、小売電気事業者(新電力会社)の電力事業参入が認められました。
新電力会社では「低料金のプラン」「基本料金0円」など、お得なサービスが提供されるケースも多く、乗り換えによって電気代を節約できる可能性があります。
大手電力会社と新電力会社の料金プランを比較してみましょう。
料金プランの比較
| 項目 | 大手電力会社A | 新電力会社B | ||
| 基本料金 ※30Aを契約 | 623.5円 | 796.06円 | ||
| 電力量料金単価 | ~120kWh | 29.8円 | 19.67円 | |
| 120kWh~300kWh | 36.4円 | 24.78円 | ||
| 301kWh~ | 40.39円 | 27.71円 | ||
上記を参考に、新電力会社への乗り換えでどのくらい節約できるのか見ていきましょう。
電力会社の乗り換えによる電気代の比較
| 期間 | 大手電力会社A | 新電力会社B | 節約額 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 10,751.5円 | 7,616.86円 | 3,134.64円 |
| 1年 | 129,018円 | 91,402.32円 | 37,615.68円 |
上記のとおり、電力会社を適切に選ぶことで電気代をコンスタントに節約できます。
電力会社によっては、夜間向けのプランも提供されています。ライフスタイルにマッチしたプランを選べば、より電気代を節約できるでしょう。
「節電しても効果がない」「数百円でもいいから節約したい」といった場合は、電力会社・料金プランの乗り換えを検討してみてください。
新電力会社については、以下の記事でも解説しています。
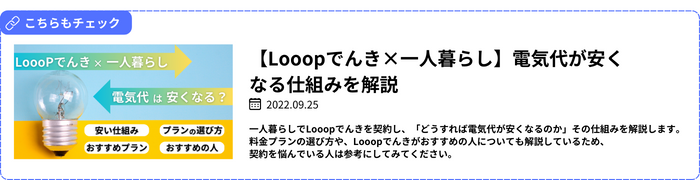
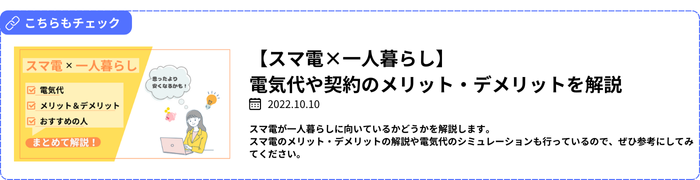
契約アンペアの見直し
電気代の基本料金は「契約アンペア」によって決まるため、見直すことでコンスタントに電気代を節約できます。
契約アンペアとは
・自宅内に流れる電気量の上限
・アンペアが大きいほど、より多くの家電製品を同時稼働できる
一人暮らしの場合、契約アンペアは20~30Aが適切とされています。過剰なアンペア数を契約しては、余計な料金を支払うことになるでしょう。
以下の記事も参考に、適切なアンペア数への切り替えも検討してください。

家電製品(エアコン・冷蔵庫・照明)の正しい使い方を覚える
家電製品の正しい使い方を理解できれば、消費電力が抑えられ、電気代の節約につながります。
家電製品別の正しい使い方
| 家電製品の種類 | 使い方 |
|---|---|
| エアコン | ・短時間の外出であればONのまま ・極端な温度設定は避ける ・自動運転で稼働させる ・フィルターは1~2週間に1回の頻度で掃除 |
| 冷蔵庫 | ・食品を詰め込まず隙間を空ける ・常温になってから冷蔵庫に入れる ・冷蔵庫の背面は隙間を空ける ・暑い時期以外は「弱」に設定 |
| 照明 | ・こまめなOFFを意識する ・LED電球に切り替える |
エアコンの消費電力が最も高まるタイミングは、設定温度に達するまでの間です。稼働直後から出力を上げるため、設定温度と室温が離れているほど、電気代は高くなります。
夏は27℃前後、冬は21℃前後を目安に設定し、余計な消費電力を発生させないよう注意しましょう。自動運転であれば、エアコンが現在の室温に応じて、効率的な出力で稼働してくれます。
エアコンの節電に関しては以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

また、冷蔵庫は冷気の効率的な循環を促すだけで、消費電力を節約できます。夏以外の時期であれば、冷気を弱に設定しても食べ物が傷むリスクを抑えられるでしょう。
省エネ家電製品への買い替え
省エネ性能が高い家電製品ほど、消費電力が抑えられ、電気代の節約につながります。2013年と2023年の家電製品を比較し、どのくらい電気代が節約できるのか見ていきましょう。
省エネ家電(エアコン)の比較
| 家電の製造年 | 消費電力/年 | 電気代/年 |
|---|---|---|
| 2013年 | 903kWh | 27,090円 |
| 2023年 | 769kWh | 23,070円 |
※電力量料金単価を30円/kWhとして算出
上記の場合、エアコン1台だけでも、年間4,000円の電気代節約につながります。テレビや照明、ドライヤーなど各家電製品を買い換えることで、中長期的に電気代を節約できるでしょう。
家電製品の省エネ性能は「省エネルギーラベル」の有無で判断できます。
※参考:経済産業省 資源エネルギー庁 小売事業者表示制度(統一省エネラベル等)とは
引越しの際は物件の断熱性・気密性も考慮する
断熱性・気密性の優れた賃貸物件であれば、エアコンの稼働効率を落とさず、電気代の節約に期待できます。
断熱性・気密性とは
・断熱性:外部の熱や冷気を遮断する指標
・気密性:建物の隙間を指す指標
エアコンは室温と設定温度の差が大きいほど、強い出力で稼働します。
外気温の影響を受けにくい賃貸物件であれば、部屋の中を一定の温度に保ちやすく、最低限の出力でエアコンを稼働させられます。
断熱性・気密性に優れた賃貸物件であれば、消費電力(電気代)の節約につながるでしょう。
一人暮らしの電気代についてよくある質問
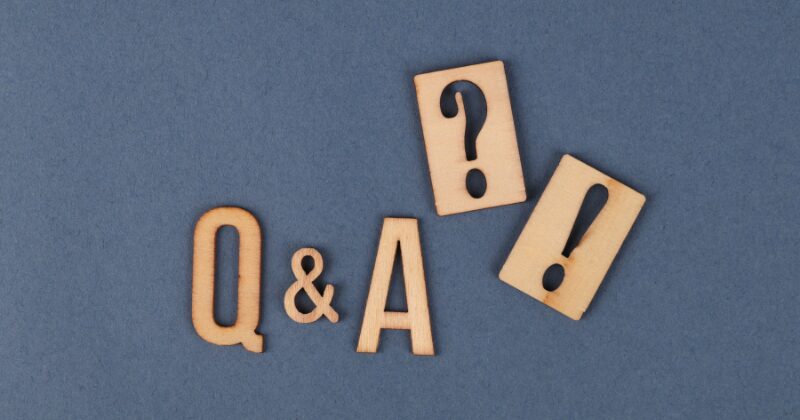
一人暮らしの電気代について、よくある質問と回答をご紹介します。
家電製品の使い方は同じなのに去年より電気代が高くなる原因は?
電気代が去年より高くなる主な原因は次のとおりです。
電気代が高くなる理由
・世界情勢の変化で燃料費が高騰した
・政府の支援対象外となった
・家電製品の手入れ不足
円安やウクライナ情勢の影響で、昨今の燃料費は高騰しています。
日本政府では、電気・ガス代の負担を減らすため、2024年から支援が行われてきました。しかし、支援の対象期間は限定的なほか、継続の有無は未定です。
そのため、時期によっては「去年よりも電気代が高くなった」と実感するかもしれません。
また、エアコンや空気清浄機は、フィルターの掃除を怠ると稼働効率が落ちます。余計な消費電力を発生させる恐れがあるため、定期的な手入れを欠かさず行いましょう。
今後も政府による電気代やガス代の支援はある?
政府による電気・ガス料金支援の継続は未定です。
しかし、2024年には「酷暑乗り切り緊急支援」という支援が実施されたため、2025年の夏以降も同様の支援が行われる可能性はあります。
一人暮らしで電気代が8,000円や10,000円を超えるのはおかしい?
時期にもよりますが、一人暮らしで電気代が8,000円や10,000円を超える場合、節電を意識すべきでしょう。
>>一人暮らしの電気代 | 1ヶ月の平均額でも解説したとおり、一人暮らしの電気代平均は6,756円です。昨今は世界情勢の影響も受けていますが、電気代が8,000円を超える場合、以下の原因に心当たりがないかチェックしてみてください。
電気代が8,000円、10,000円を超える原因
・テレワークの頻度が増えた
・エアコン節電のため、頻繁にON / OFFを繰り返した
・新しい賃貸物件に引越した(断熱性・気密性が低くなった)
電気代は、電気の使用量(消費電力)に応じて増えていきます。テレワークの日数が増えた場合、エアコンやPCの稼働により電気代が高くなっているかもしれません。
また、エアコンはON / OFFを繰り返すと余計な電力を消費します。断熱性・気密性の低い賃貸物件も同様、エアコンの出力が高まる原因となり、電気代が高くなります。
詳しくは以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

電気代が下がらない場合は電力会社・料金プランを乗り換えよう!
一人暮らしの場合、1ヶ月の電気代平均は6,756円です。季節や地域によっても変動しますが、平均額を大きく上回る場合、節電を心がけましょう。
ただし、個人でできる節電には限界があります。どれだけ節電しても電気代が下がらない場合は、電力会社・料金プランの乗り換えも検討してみてください。
基本料金や電力量料金単価(使用量に応じた料金単価)が下がれば、コンスタントに電気代を節約できます。
どの電力会社・料金プランが自分に合うか、判断が難しい場合は「くらしテク」に相談してみましょう。電話1本でコンシェルジュによる最適なプランを提案してもらえます。