
社会人はお金を使うシーンが多く、支出が多くなりがちですよね。中には、うまく貯金ができない、続かないという人もいるかもしれません。
そこで今回は、生活費の平均を知って自分の支出額と比較しつつ、上手に貯金できる方法を紹介します。男女別の生活費や社会人ならではの節約術などをチェックしてみてください。
【社会人の生活費】男女別の生活費内訳
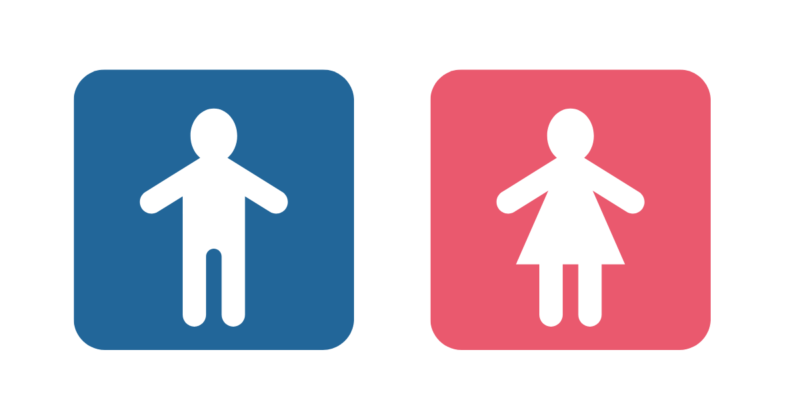
まずは、生活費の内訳と平均額から見ていきましょう。男女それぞれ生活費の平均額が違うので、個別に紹介します。
女性の生活費平均
| 費用の内訳 | 費用 |
| 食費 | 34,127円 |
| 住居費 | 32,188円 |
| 光熱・水道費 | 11,005円 |
| 家具・家事用品 | 7,511円 |
| 被服・履物 | 8,837円 |
| 保険医療 | 6,823円 |
| 交通 | 3,160円 |
| 自動車関係 | 9,008円 |
| 通信 | 7,811円 |
| 教養娯楽費 | 15,624円 |
| その他(理美容品、身の回り用品、たばこ等) | 35,321円 |
| 合計 | 171,415円 |
女性の場合、食費は比較的少ないですが、光熱・水道費やその他の費用が多くなっています。これから節約しようと考えている場合、このような数値も参考にしてみてください。
男性の生活費平均
| 費用の内訳 | 費用 |
| 食費 | 44,720円 |
| 住居費 | 29,071円 |
| 光熱・水道費 | 9,966円 |
| 家具・家事用品 | 3,891円 |
| 被服・履物 | 4,578円 |
| 保険医療 | 4,916円 |
| 交通 | 4,312円 |
| 自動車関係 | 12,110円 |
| 通信 | 9,278円 |
| 教養娯楽費 | 19,546円 |
| その他(理美容品、身の回り用品、たばこ等) | 24,567円 |
| 合計 | 166,955円 |
男性の場合、食費や通信、教養娯楽費などの費用が高いようです。どれも節約しやすい費用なので、生活費を抑えようと考えている人は、これらを意識してみましょう。
ここで紹介した生活費はあくまでも「平均額」です。都心部の場合は住居費や食費などが高額になりやすいので、この表を目安にして、おおよその生活費を把握してみましょう。
余裕ができれば必ず貯金
決められた金額でやりくりする癖をつけるためにも、お金に余裕があれば少額でも貯金へ回すことがおすすめです。
例えば、あらかじめ設定した金額(生活費や貯金額など)で生活し、毎月2万円の余裕が発生したとします。この2万円を生活費や交際費、食費などへ回すと生活水準を上げることになります。
一度上がった生活水準はなかなか下げられません。人によっては、昇給やボーナスの支給の際に、お金を浪費してしまう恐れがあります。
浪費癖をつけないためにも、お金に余裕があれば貯金へ回す癖をつけていきましょう。
【社会人の生活費】家賃の目安は収入の1/3~1/4

家賃を1/3~1/4に抑えるべき理由は、収入から生活費(家賃以外)を引いたとき、貯金もしつつ余裕で支払える額になるからです。
例えば、毎月の収入が20万円の場合、生活費(食費や交際費、交通費など)が12万円、目標貯金額を3万円とすると家賃5万円の物件に住めます。
ただし、これはあくまでも目安なので、家賃を決める際は収入と生活費、目標貯金額から逆算して決めましょう。さらに、地域によって家賃相場も異なるため、住む場所に合わせて生活費や貯金額を調節する必要があります。
【社会人の生活費】誰でもできる節約方法

社会人の場合、クレジットカードや電子マネー、自治体の制度などをうまく活用すると、上手にお金を節約できます。
節約については以下の記事も参考になるので、一度チェックしてみてください。
クレジットカードを使った節約
クレジットカードは利用することでポイントが付与されるケースが多いです。日用品や食料はもちろん、交通費、光熱費などもクレジットカードで支払いができます。
中でも、固定費(光熱費や携帯料金、通信費、家賃)の支払いはクレジットカードを利用しましょう。これらの費用は日頃の買い物よりも金額が大きいため、付与されるポイントも多くなります。
例えば、毎月の固定費合計が7万円、ポイント還元率が1%の場合、1か月あたり700ポイント(1ポイント=1円)貯まっていきます。年間8,400円相当のポイントが貯まる計算です。決して少ない額ではありません。
家賃に関しては、クレジットカードで支払える賃貸物件を探しましょう。徐々に増えてはいますが、不動産会社に相談して確認する必要があります。
注意点として、クレジットカードの契約をする際は年会費のかからないタイプを選びましょう。さらに、付与されるポイントは期限付きのケースが多いです。必ず利用期限を確認して、ポイントは使い切る必要があります。
節約におすすめのクレジットカード
- 還元率は1.00~3.00%
- 年会費無料
- 入会時特典として数千ポイントが付与される
- 審査のハードルが低い
- 電子マネーも使える(ポイント付与あり)
- 公共料金の支払い可能
- ふるさと納税の寄付もできる(ポイント付与あり)
- 還元率は0.5~5%
- コンビニ(ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート)での利用は最大5%還元
- 年会費無料
- 5種類の電子マネー(WAONやPITAPAなど)が追加可能
- ナンバーレス(カードに番号の記載がない)のためセキュリティも安心
- 還元率は1.2~4.2%
- リクルート提携サービスで利用するとポイント還元率アップ
- 年会費無料
- 携帯料金、公共料金、交通費などの支払いが可能
- 貯まったポイントはPONTAポイントへ変換できる
- 新規入会+利用で8,000ポイント付与(2021年4月現在)
クレジットカードでの浪費に注意
節約を意識してクレジットカードを利用する場合は、同一カードでの交際費や趣味などの支払いはおすすめしません。特に、限度額が50~100万円と高額に設定している場合は、利用シーンを絞りましょう。
ポイントは付与されますが、翌月に支払いきれなくなる恐れがあります。クレジットカードは気軽に使えて便利ですが、現金が目に見えないので、ついつい浪費してしまいがちです。
固定費や食費以外でもクレジットカードを利用したいという場合は、別のカードを契約して、限度額を最低金額に設定することをおすすめします。もしくは、電子マネーを利用して、毎月の支出額をコントロールしましょう。
リボ払いは特に注意しなければなりません。毎月の支払額は少なくなりますが、利息が高くなり支払いきれないケースもあります。場合によっては、利息のみしか支払っていない状態となり、元金が減らないといったケースもあるので注意しましょう。
電子マネーを使った節約
年始マネーは日頃の買い物以外にも、交通費や交通費などの支払いにも利用できます。ポイントが付与される電子マネーも多いので、節約にはおすすめです。
電子マネーの上手な使い方
電子マネーは、あらかじめチャージした金額内で支出の管理ができます。そのため、予算内で生活費をやりくりしようと考えている人にはおすすめの節約方法です。
電子マネーでうまく節約するには、利用シーンごとに電子マネーを使い分けます。例えば、コンビニ用、ドラッグストア用、公共交通機関用などです。あまり多すぎると面倒なので、2~3用途を目安にしましょう。
用途別に使い分ける際は、シーン別のポイントの貯まりやすさで電子マネーを選びます。例えば、コンビニで使うと還元率が高い、特定のネット通販で買い物すると高還元などです。具体的には、以下のような電子マネーを参考にしてみてください。
WAON
- イオン系列のお店で使うとポイント2倍
- 指定店舗にリサイクルゴミを持ち込むとポイント付与
- 貯まったポイントは電子マネーに変換可能
- ドン・キホーテで使うと高還元
- 前年の利用額に応じて還元率が変動(50万円以上で2%、100万円以上で3%など)
- 会員特典として、家電製品の無料引き取りや購入金額に応じた特典ももらえる
- セブンイレブンの対象商品購入でボーナスポイント付与
- セブン銀行との取引でもポイントが貯まる
- クレジットカードからのチャージでポイントが貯まる
家賃助成制度を利用した節約
家賃助成制度とは、ある条件を満たしていることで、家賃の補助を受けられる仕組みです。家賃は固定費の中でも大きな割合を占めているので、積極的に節約へ利用しましょう。
また、家賃助成制度には所属している会社の福利厚生、自治体が行っている取り組みなど種類があります。それぞれどのような仕組みなのか見ていきましょう。
福利厚生による家賃助成制度
会社から家賃の補助を受けるには、特定の条件を満たしている必要があります。例えば、会社から自宅までの距離が〇〇㎞離れている、会社指示による赴任、家賃の高額なエリア(東京都内など)では〇万円補助などです。
会社HPの雇用条件や就業規則などに記載されているので、チェックしてみてください。
業績次第では、会社からの補助を受けられなくなる恐れがあります。そのため、入社時には福利厚生に盛り込まれていたとしても、数年後には無くなっている可能性があることも理解しておきましょう。
自治体の家賃助成制度
一部の自治体では、住居者の家賃負担軽減や定住促進を目的として家賃補助制度を導入しています。この制度では単身者やファミリー層、高齢者などさまざまな世帯が対象です。特に、過疎化が進んでいる地方自治体では導入されているケースが多くあります。
また、家賃助成制度を受けるには、特定の条件を満たさなければなりません。例えば、30歳未満の勤労している単身者、家賃が9万円以下の物件に住んでいる、家賃を滞納していないなどです。
自治体によって条件は異なるので、自治体のHPなどで確認してみましょう。
サブスクを使った節約
サブスク(サブスクリプション)は月額制料金で特定のサービスを受けられる仕組みです。定額で商品(映像・音楽コンテンツや日用品、食品)を購入した場合よりも、リーズナブルなケースもあります。そのため、節約を検討している人には利用してほしいサービスの1つです。
ここでは、節約に効果的なおすすめのサブスクを紹介します。
- 418円(税込)/ 月で500冊以上の雑誌が読める
- 年間プランは3,960円(税込み)/ 月
- 毎月雑誌を購入している人におすすめ
- 雑誌カテゴリーは17種
- 1,980円(税込)/ 月でマスクを利用できる
- 送料無料で月一回、50枚入りのマスクが2箱(計100枚)届く
- 職業柄必要な人や、花粉症などの疾患を抱えている人におすすめ
- 家具、家電のサブスク
- 最低500円(税込)/ 月から家具、家電を利用できる
- 返却期限なし
- 気に入ったものは購入できる(これまで支払った月額料金から差し引いた額で購入)
- 気になる家電、家具をお試ししたい人におすすめ
家具・家電のサブスクは長期間同じ商品を利用し続けていると、利用金額が定価を上回ってしまいます。そのため、少しでも別の商品が気になったときは交換する、定価の半額に達した際には購入するなど、しっかり決断しましょう。
また、契約期間が決まっているサブスクもあります。例えば、1年契約のサブスクの場合、途中で解約しようとすると手数料が発生するケースもあるので注意が必要です。
【社会人の生活費】貯金額相場を知って生活上手

貯金を始める際は、目標金額の設定が大切です。モチベーションにつながるほか、具体的な目標を設けることで毎月の生活費を具体的に設定でき、浪費癖も防げます。
金融広報中央委員会(家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和元年調査結果)によると、20代の平均貯金額は198万円でした。
この貯金額を大学卒業後、社会人1年目の23~29歳までの7年間で割ると、年間およそ28万円、月々約2.4万円です。この貯金額であれば、毎月の収入が20万円であったとしても、必要以上に浪費しなければ無理せず貯められるでしょう。
まとめ
社会人は出費がかさむシーンが多いです。そのため、各シーンごとに節約へつながる術を持っておくことが大切です。ただし、闇雲に節約する、貯金するを繰り替えしてもモチベーションの維持が難しくなります。
上手に節約・貯金を繰り返していくためにも、具体的に目標を設定し無理しないことを意識しましょう。












