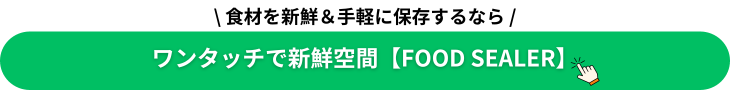投稿日:2023年5月4日 | 最終更新日:2024年8月23日

「自炊=安い」というイメージを持っていても、想定より高くつくことがあります。
そこで今回は、「自炊はコスパが悪いのか?」「悪くなる原因は何なのか?」など、自炊の気になるポイントを解説します。
簡単にできる節約方法も解説しているので、コスパアップを目指す人は参考にしてみてくださいね。
また、最後は自炊・中食(お惣菜など)・外食の費用も比較しています。
他の食事方法と比較して、自炊はどのくらいコスパが良いのかもチェックしてみましょう。
自分の食生活と照らし合わせると、「自分に合う食生活」「これからの改善方法」などが見えてくるはずです。
<栄養&手軽さを求めるなら「ナッシュ」がおすすめ!>
○栄養管理された冷凍弁当が自宅に届く(糖質量30g以下、塩分量2.5g以下)
○1週間に最低2品の新メニューが提供される
○電子レンジでチンするだけ!
○容器は燃えるゴミにポイ♪
○1食あたりの価格は約500円
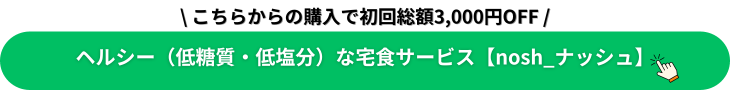
コスパが悪い理由は「お金・時間・手間・やる気」の不足
食事におけるコスパは、「お金・時間・手間・やる気」の4つをバランス良く満たすことが大切です。
食材費を安く抑えても、調理の時間・手間がかかっていれば低コスパと言えます。
さらに、お金・時間・手間のコスパが高くても、調理の「やる気」がなければ自炊につながりません。
自炊における「良コスパな食事」を続けるには、「お金・時間・手間・やる気」をバランス良く維持する必要があります。
一人暮らし×自炊でコスパが悪くなる6つの理由

一人暮らしの自炊でコスパが悪くなる原因は、以下の6つが考えられます。
自炊のコスパが悪くなる6つの原因
著者の体験も踏まえ、コスパが悪くなる理由を解説します。
食材費が割高
1食分を目安に食材を購入してしまうと、食費は割高になってしまいます。
たとえばキャベツの場合、「1玉213円」と「1/4カット73円」といった価格で販売されます。
1/4カットのキャベツを1玉分にすると、価格は1玉292円です。
※出典:イオン 東北ネットスーパー
食費を安く済ませようと1食分の食材だけ買ってしまっては、1食あたり400~500円ほどかかるかもしれません。
著者の場合、割高の食材を買いつつ、品数も多く作ってしまい、1食あたり500~600円ほどになったこともあります。お弁当やお惣菜の方が安くなるケースもあるため、食材費も含めて計算しましょう。
もちろん、「冷蔵庫の容量」や「1回の食事で食べきれない」といった問題は出てきます。
これらの問題解決に関しては、以下で詳しく解説するので参考にしてみてください。
自炊で食材を余らせる
「食材を余らせる」=「食費を無駄にしている」につながります。
食材が余る原因を挙げていくので、心当たりのある人は食材の使い方を見直してみましょう。
食材が余る原因
●食材の保存方法が間違っている
●保存の効く食材を選んでいない
●献立を考えずに買っている
野菜や肉類など生鮮食品の場合、正しい保存方法を知らないと長期保存できません。結局、使い切れないまま冷蔵庫に放置されます。
さらに、食材といっても生鮮食品がすべてではありません。缶詰や冷凍食品など、長期保存に向いた食材もあります。
うまく使い分けて、食材の無駄を省きましょう。
また、献立を考えず安売りしている食材を買うのもNGです。どれだけ安い食材も、使わなければ余計な出費になります。
大切なのは、「保存」と「献立の計画」を考えて買い物することです。
旬の時期に食材を買えていない
旬の時期を考えずに食材を買ってしまうと、1食あたりの費用はお惣菜・お弁当と大差ありません。
多くの食材には「旬」があり、旬の時期は収穫量や流通量が多くなるため食材が安くなります。
どのくらい価格が変わるのか、農林水産省のデータをもとに見ていきましょう。
食材の価格(円/㎏)について
| 季節 | たまねぎ(3~4月) | トマト(6~8月) | キャベツ(12~6月) |
|---|---|---|---|
| 春 | 228円 | 703円 | 183円 |
| 夏 | 273円 | 660円 | 221円 |
| 秋 | 238円 | 855円 | 164円 |
| 冬 | 235円 | 727円 | 133円 |
※各季節の平均価格
※出典:農林水産省 食品価格動向調査(野菜)
上記のとおり、旬の時期以外は食材の価格が高くなりやすいです。
コスパアップのためにも、旬を意識して買い物してみましょう。
▼以下のサイトでは、食材の旬をカレンダー形式で紹介してくれています。
自炊の「休日」を作らない
自炊の「休日」を作らないと、「手間・時間・やる気」のコスパが悪くなります。
自炊を毎日する必要はありません。仕事や学業で疲れていると、やる気が起こらない日もあります。
お惣菜やお弁当に頼る日があっても、自炊は続けられます。
休める日を適度に作って、コンスタントに自炊できる環境作りに意識を向けてみましょう。
時間と手間がかかりすぎる
慣れない人にとって、自炊は時間と手間がかかり、コスパが悪くなりがちです。
一人暮らしでは、以下の工程をすべて自分でこなさなければなりません。
自炊の工程
1.食材の購入(10~20分)
2.調理(30~40分)
3.食事(20~30分)
4.後片付け(約10分)
自炊に慣れていないは献立がまとまらず、食材の購入~調理により時間がかかるかもしれません。
仕事から帰宅して上記のような工程を踏んでいては、疲れてしまい毎日続けられない可能性もあります。
著者の場合、初めての頃はレシピを見ながらの調理だったので、1回の調理に40分はかかっていました。
調味料のコストを計算していない
意外と忘れがちなのが「調味料」にかかる費用です。
一般的なスーパーで売られている調味料の価格を見ていきましょう。
調味料の価格
| 調味料 | 1kg・1Lあたりの価格 | 大さじ1あたりの価格 |
|---|---|---|
| 砂糖 | 224円 | 3円 |
| 塩 | 97円 | 2円 |
| 酢 | 534円 | 8円 |
| 醤油 | 289円 | 4円 |
| 味噌 | 314円 | 5円 |
| 合計 | 1,458円 | 22円 |
上記の調味料を使う場合、一食分にかかる調味料の費用は20円以上と想定できます。
小さい容器に入っている調味料は割高なので、より食費がかさむでしょう。
「計算しているより食費が高い」「なぜか出費がかさむ」といった人は、調味料の費用も含めて計算してみてください。
一人暮らし×自炊のコスパをアップ!6つの簡単節約術

自炊のコスパをアップさせる節約術を6つ解説します。
「いつもしている自炊」に「ちょっとしたコツ・テクニック」を追加するだけで、自炊のコスパは良くなります。
自炊のコスパアップ!簡単節約術
作り置きで「無駄・手間・時間」を省く
作り置きは食材の「無駄」と自炊の「手間・時間」を省く、コスパアップに欠かせないポイントです。
作り置きのメリット
●2~3日分を作り置きすることで捨てる食材を減らせる
●作り置きがあると調理の手間と時間を省略できる
「食材費が割高」でも解説したように、1食分の調理は食材を余らせやすく、食費の無駄につながります。
しかし、作り置きで2~3日分の食事を調理しておけば、まとめ買いした食材を無駄にすることなく調理できます。
また、作り置きがある限り、毎日自炊する必要もありません。
自炊をするにしても、簡単な調理でおかず1~2品追加する程度で済みます。
著者おすすめの作り置きメニューを紹介するので、参考にしてみてくださいね。
おすすめの作り置きメニュー
| メニュー | 日持ち(冷蔵) | おすすめの理由 |
|---|---|---|
| レンコンのきんぴら | 約7日 | ・日持ちしやすく ・お弁当のおかずにもOK |
| 肉そぼろ | 3~5日 | おかず、丼、トッピングなど、バリエーションが豊富 |
| なすの南蛮漬け | 約5日 | 電子レンジだけで調理可 |
| ハンバーグ(タネ) | 1日 (冷凍で約2週間) | 焼くだけでメイン料理になる |
| カレー | 約3日 | ・ご飯を用意するだけでOK ・初心者にも作りやすい |
副菜は作り置き、メイン料理をお惣菜といった組み合わせもおすすめです。
食材は冷凍保存して無駄を防止
余った食材は冷凍保存して、食費の無駄を予防しましょう。
肉・野菜それぞれの冷凍方法・コツを解説するのでチェックしてみてください。
肉の冷凍方法・コツ
●パックから取り出して、肉に付いた水分をキッチンペーパーで拭き取る
●冷凍する際は密閉保存袋がおすすめ
●小分けする場合はラップで包む
●金属製トレイの上に置き、急速冷凍で品質を保つ
※冷凍保存の目安は約1ヶ月
冷凍保存する際は、なるべく肉が空気に触れないよう気を付けてください。
空気は肉の酸化・乾燥の原因となり、味が落ちます。
また、約1ヶ月冷凍保存できるといっても、空気に触れていると劣化は進みます。
なるべく早く調理して、傷まないようにしましょう。
では、野菜の冷凍方法・コツを解説します。
野菜の冷凍方法・コツ
●野菜の水分はしっかり拭き取る
●金属製トレイの上において、急速冷凍で野菜の品質を保つ
●下茹でした場合は粗熱を取っておく
●繊維質、水分の多い野菜は冷凍に向かないので、そのまま冷凍するのは避ける
キャベツやトマト、ニンジンなどは冷凍に適していません。
しかし、キャベツ・ニンジンはカットして冷凍することで、独特な繊維質を抑えられます。
水分の多いトマトや大根などは、潰してソースにしたり、すりおろしたりしておくと冷凍できます。
一方、葉物野菜は冷凍に適した野菜です。
下茹でして冷凍しておくと、調理の下ごしらえを省略できますよ。
チラシアプリで食材費を節約
チラシアプリを使えば、食材費を効率的に節約できます。
チラシアプリとは、スーパーやドラッグストアなどの「お得情報」をチェックできるアプリです。
チラシアプリのメリットを見ていきましょう。
チラシアプリのメリット
◎特売情報をアプリ一つでチェックできる
◎わざわざ店舗まで足を運んで値段を見る必要がない
◎クーポンが配信されるチラシアプリもある
チラシアプリがあれば、複数の店舗を周って安い食材を探す必要はありません。
自宅で目星を付けて、安い食材を買いに行けます。
以下は、おすすめのチラシアプリです。
トクバイは全国7割以上の食品スーパーが掲載されるチラシアプリです。
お得情報をアプリでチェックして、購入すべき食材をピックアップしましょう。
献立通りの買い物で無駄遣い防止
あらかじめ献立を決めておけば、余計な買い物による無駄遣いを防げます。
買い物で出費がかさむ原因は「予定にないものを買う」ためです。
たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
余計な出費の例
●なんとなくコンビニに入って必要のないものを買う
●スーパーで予定にないお菓子やドリンクを買う
●普段は買わない「珍しい調味料」を買う
●「特売」「安売り」などと書かれた商品を衝動買いする
調味料や特売品などは問題ないように思うかもしれませんが、「使う予定がないもの」であれば無駄な出費です。
どれだけ安くても、食材として使わなければ意味がありません。
買い物をする際は献立を決めて、買う食材をピックアップすることが大切です。
買い物用の財布を作り、必要なお金だけ入れておくというのもおすすめですよ。
電子レンジで光熱費&手間・時間を節約
電子レンジで野菜の下処理を行えば、光熱費&調理の手間・時間を節約できます。
ガスコンロで下茹でするよりも、電子レンジの方が短時間で野菜に火を通せます。
電子レンジとガスコンロで、野菜(かぼちゃ)の下処理にかかる光熱費を比較してみましょう。
電子レンジとガスコンロの光熱費
| 種類 | 電子レンジ | ガスコンロ |
|---|---|---|
| 調理時間 | 5分 | 20分 |
| 光熱費 / 1回の調理 | 約2円 | 約7円 |
| 光熱費 / 1ヶ月 | 約60円 | 約210円 |
野菜の種類(ニンジンやジャガイモなど)によっては、下茹でだけで10分以上かかります。
一方、電子レンジであれば2~5分程度で下茹でを済ませられます。
コストの節約にもつながるので、自炊のコスパアップを目指す方は電子レンジで下処理を済ませましょう。
【自炊なしで食費節約】お惣菜+炊飯
自炊は、必ずしも調理にこだわる必要はありません。割引されたお惣菜を買い、お米だけ炊いておくと、割安で食事を用意できます。
著者の場合、仕事帰りにお惣菜を買い、以下の献立で食事を用意していたこともあります。
お惣菜+ご飯の献立例
・単品のお惣菜×3品(1品あたり70~100円)
・インスタントの汁物(1杯あたり約20円)
・ご飯 (1杯あたり約45円)
スーパーでは、夕方以降にお惣菜が割引されるケースが多いです。単品のお惣菜であれば、1人分の食材が割安で手に入る可能性もあり、1食あたり300円ほどで用意できます。
手間と時間がかからず、費用の節約にもつながります。
お米を炊く量がわからない場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

一人暮らしの「自炊・中食・外食」を比較!自炊は本当に安い?

一人暮らしにおいて自炊はどの程度コスパが良いのか、中食・外食と比較しながら解説します。
自炊・中食・外食の費用
結論として、自炊は中食(お弁当やお惣菜)と費用の差はほとんどありません。
一人暮らしの食費について、自炊・中食・外食を比較してみましょう。
自炊・中食・外食の費用を比較
| 項目 | 自炊 | 中食 | 外食(昼・夜) |
|---|---|---|---|
| 1食分 | 約300円 | 約300~500円 | 約500~1,000円 |
| 1ヶ月分 | 約27,000円 | 約27,000~45,000円 | 約30,000~60,000円 |
中食は特売品やタイムセールなどを狙えば、自炊との差はほとんどありません。
一方、外食は調理・後片付けなどの手間がかからないため、費用のウェイトが大きくなります。
自炊・中食・外食のメリット・デメリット
自炊・中食・外食のメリット・デメリットを解説します。
自炊・中食・外食のメリット・デメリット
| 項目 | 自炊 | 中食 | 外食 |
|---|---|---|---|
| メリット | ・費用が安い ・栄養バランスを調整できる | ・外食より安い ・調理の手間がない | ・準備の手間がない ・プロの料理が食べられる |
| デメリット | ・調理の手間と時間がかかる ・慣れないと続かない | ・費用が割高 ・品切れの可能性あり ・ゴミが出る | ・自炊や中食より割高 |
費用・手間のバランスを考えると、自炊+中食の組み合わせがおすすめです。
自炊が毎日できれば、費用はグッと節約できます。
しかし、慣れないうちは続かない可能性もあるので、中食も選択肢に入れてみましょう。
前述したように、特売品やタイムセールを狙えば、自炊と変わらない費用に抑えられますよ。
1人暮らしの食費平均は?
総務省統計局の家計調査によれば、一人暮らしの食費平均(1ヶ月あたり)は以下のとおりです。
・食費全体:39,069円
・外食 :7,840円
・中食 :7,536円
※出典:総務省統計局 2022年度 家計調査
上記を目安に、自分の食費がどのくらい高いのか確認してみましょう。
【自炊は無理!】そんなときは価格&栄養バランスが良い「冷凍弁当」
冷凍弁当とは、カロリーや塩分など、栄養バランスが整えられた冷凍食品です。
価格帯は中食レベル(500円前後)ですが、外食ほどお金がかからず、自炊にかかる手間・時間を節約できます。
冷凍弁当のメリット・デメリットは次のとおりです。
冷凍弁当のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・チンするだけで食べられる ・オンラインショップで買える ・保存期間が長い(冷凍6ヶ月程度) ・手頃な価格帯(400~600円) | ・1食分の量を調整しにくい ・冷凍庫を圧迫する ・ゴミの量が増える |
著者のおすすめは、宅食サービスの「ナッシュ」です。
糖質量は30g以下、塩分量2.5g以下、栄養士により管理されたお惣菜を定期的に自宅へ届けてもらえます。
必要のない週はスキップできるため、調整しやすいのも嬉しいポイントです。
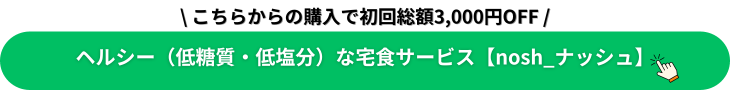
【結論】「コツ」を知らない自炊はコスパが悪くなる!
1人暮らしの自炊は、「コツ」を知らなければコスパが悪くなるため注意が必要です。
たとえば、「1食分の食材を買う」「旬や量を考えずに食材を買う」などを続けていては、手間も費用もかかり、コスパが良いとは言えません。
「コスパの良い食事」として重要なのは、「いかに楽をしながら節約するか?」を意識することです。
そのため、著者のおすすめは「自炊+中食(お惣菜やお弁当)」の組み合わせで、費用・手間・時間のコスパをアップさせる方法です。「一品だけお惣菜」「1週間に1日だけお弁当」など自炊の休日を設けることで、やる気も維持しやすくなります。
適度に休みつつ、「自炊のコスパをアップさせる5つの簡単節約術」で解説した節約方法も試してください。